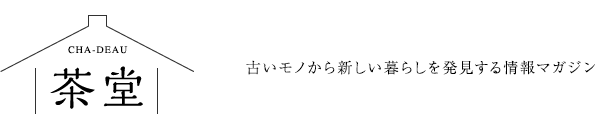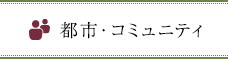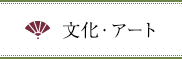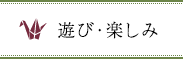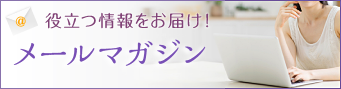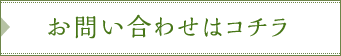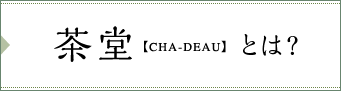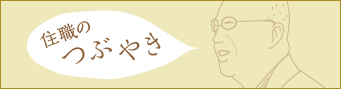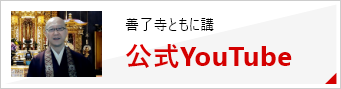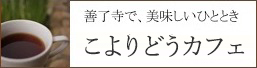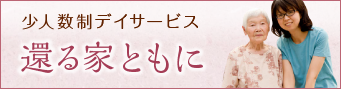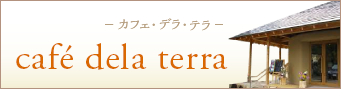- 季節・暦
- 2025年4月29日
いずれアヤメかカキツバタ・・・かショウブ?
今回はショウブについて、最近知って驚いたことを書いてみようと思います。
◎ショウブ湯
ショウブと言えば5月5日、子どもの日のショウブ湯です。端午の節句にお風呂に入れる風習のある、香りのよいシュッと細長い葉っぱ。見たこと、使ったことのある人が多いのではないでしょうか。花はアヤメに似た紫色の・・・

こんな花を思い浮かべますよね?
ところが、実はこれ違うんですって。あの葉っぱと花は別のもの。
ショウブ湯に使われるショウブはサトイモ科のショウブで、葉の形は似ていますがこんな花はつきません。ガマの穂のような棒状の花がつきます。同じサトイモ科の水芭蕉から白い部分をとった形と表現してもいいかもしれません。いずれにせよ目立ちません。

では思い浮かんだあの紫色の花は?と不思議になります。あれはアヤメ科「ハナショウブ(花菖蒲)」です。日本に自生していたノハナショウブ(野花菖蒲)を改良してつくられた園芸種です。同じような葉で、同じような名前、なんて紛らわしいんでしょう。
ハナショウブに薬効はありませんが、似たような葉と名前をもつ「ハナショウブ(花菖蒲)」が、後世になって子どもの日に飾られたり、描かれたりするようになりました。
サトイモ科ショウブ属
ショウブ(菖蒲)・・・穂状の花がつく。葉に芳香があり、ショウブ湯に使われる。
アヤメ科アヤメ属
ハナショウブ(花菖蒲)・・・華やかな花が咲く。葉に芳香なし。
◎「菖蒲」
これをなんと読みますか?
私はずっと「ショウブ」と呼んでいました。だって「菖蒲園」は「ショウブエン」で「菖蒲湯」は「ショウブユ」でしょう。だから、「いずれ菖蒲か杜若」は「いずれショウブかカキツバタ」だったんです。私の中では。
ところが、ここにも思い込みの落とし穴がありました。
「菖蒲」は「ショウブ/アヤメ」どちらとも読みます。アヤメの漢字表記には「文目」もあり、特に区別したいときはこちらをアヤメとして使うこともあります。
「いずれ菖蒲か杜若」は「いずれアヤメかカキツバタ」が正しい読み方です。どちらも同じくらい優れていて甲乙つけがたいという意味です。アヤメもカキツバタも花の形がよく似ているのです。
ここでアヤメとハナショウブを比べず、カキツバタを出してくるところがにくい。カキツバタはハナショウブに似た日本に自生する植物です。古くは万葉集にも読まれたり、屏風絵になったり、日本人に馴染み深い水辺のお花です。
アヤメ科アヤメ属
アヤメ(菖蒲/文目)・・・花弁に網目のような模様がある。草地に自生する。
カキツバタ(杜若)・・・花弁の下に白っぽい線がある。浅い水中で育つ。
ハナショウブ(花菖蒲)・・・花弁の下に黄色い線がある。湿地を好む。
ノハナショウブ(野花菖蒲)・・・ハナショウブの原種。日本の湿地に自生する。
◎もとをただせば
どうしてこんなに呼び方や表記が入り組んでいるのでしょう。
そもそも薬湯として使われるサトイモ科のショウブを「アヤメ」と呼んでいたことに始まります。
江戸時代、薬草のアヤメに葉が似ていて、きれいな花が咲くものをハナアヤメ(現在のアヤメ)として愛でるようになりました。始めの頃は、薬草のアヤメをアヤメグサとして区別しました。ところが、時間が経つにつれて、ハナアヤメだけを知っている人が増え、呼び名もハナアヤメから、ただのアヤメと呼ばれるようになったのです。
それではアヤメグサの呼び方に困るということで、アヤメの漢字表記「菖蒲」を音読みして「ショウブ」と読みましょうということになったようです。
続いて、ノハナショウブを品種改良したハナショウブが現れます。やはり葉の形は似ていますが、サトイモ科のショウブより、ハナショウブの方が華やかで、大衆の認知度が高まっていきます。すると五月人形とハナショウブを一緒に飾ったり、子どもの日のお知らせにハナショウブのイラストを使ったりして誤用されるようになっていきました。またしても、お花に押されて肩身が狭くなっているショウブなのでした。思い込みって怖いですね。
参考文献
「APG巻の植物図鑑Ⅰ」邑田仁監修 北隆館 2014
「花の事典和花 日本の花・伝統の花」 講談社 1993
「野に咲く花便利帳」稲垣栄洋監修 主婦の友社 2016
「知識ゼロからの植物の不思議」稲垣栄洋 幻冬舎 2019
「重井薬用植物園」https://www.shigei.or.jp/herbgarden/album/syoubu/album_syoubu.html
寄稿者 ほりえりえこ
湘南在住。小学生の娘と暮らしてます。今を大切に。日々のなぜ、なに、どうしてを大切に。心が動いたこと、子どもに伝えたいことを書いています。