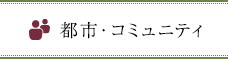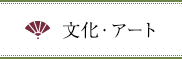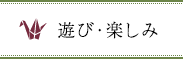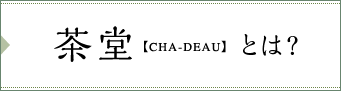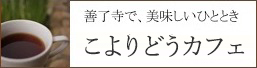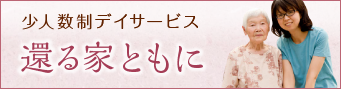先日、4月29日に、善了寺の聞思堂並びに、本堂・客殿・デイサービスの設計監理を頂いた建築家 大岩剛一先生の一周忌をお迎えしました。
この、世情不安の中で、剛一先生のことを思うとき、本当に有り難い出遇いであったと思います。今も、先生とご一緒した建築の中で、たくさんの方々とともに多くの学びを頂いています。心から感謝申し上げます。
さて、この一周忌にあわせて、弟さんでもある、辻信一先生から、素敵な贈り物を頂きました。みなさんとご一緒に味わい、学ばせて頂ければと思い、ここに掲載いたします。
大岩剛一先生は、決して過去の思い出ではありません。今も尚、私たちと共にあるからこそ、素敵な贈り物を頂くご縁が恵まれているだと思います。
素敵な学びをご一緒に、後日、私が学ばせて頂いたことを書いていきたいと思っています。まずは、辻先生の贈り物をゆっくり読んでみてください。
辻信一先生には、心から感謝申し上げます。
以下、辻信一先生からいただいた文章となります。
*2019年8月9日にカフェゆっくり堂で実施された高橋源一郎さんとの公開研究会「”雑”から”あいだ”へ」での辻さんの発言をもとに構成されています。
生と死の「あいだ」 兄・大岩剛一の一周忌によせて
お盆が近づいているんで、それにちなんだ話です。若い人はお盆ってなんだか知っていますか。ご先祖たちの魂が帰ってくるのを迎える。生者と死者が交流する、といってもいいでしょう。ということで、今日は生と死の「あいだ」っていうことに触れておきたいなと思います。
ぼくの兄、大岩剛一がこの四月の末に亡くなりましてね。ほんとに仲の良かった大好きな兄ですから、その前後からの半年あまりっていうのはぼくにとって、何ていうのかな、英語で言うとインテンスでありながら、かつ非常に充実した、ある意味、楽しい日々だったんですね。そういう特別な時間だったなと思います。亡くなる前、去年の暮れぐらいからぼくの体にも心にもいろんな変化が起こってたんですが、亡くなってからのこの数ヶ月は、すごく変なことがいっぱい起こった。魂がちょっとこう抜けちゃったような感じなんですよ。
考えてみれば、ぼくと兄とは昔から非常に親しくて、ある意味じゃ魂を共有していたようなところがあったはずだから、二人のうちの片一方がいなくなっちゃったときに、共有していた魂がどうなっちゃうのかなって考えれば、まあ、そのぐらいのことはあるよなっていう感じはしました。
この前、ドイツから来日した植物療法士の友人にその話をしたら、彼はいや全くその通りだ、と言う。実際にそういうことはあって、親しい人の死ととともに、共有していた魂の一部が死者とともに行ってしまうので、魂が抜けた状態になる。でも、大丈夫、しばらくすると、ちゃんと戻ってくるから、と断言してくれて、とてもうれしかった。戻ってくることもだけど、何より、根源的な何かをやっぱり共有していたんだ、というのがうれしかった。
誰でも死というものを通して、生と死の「あいだ」っていうのを考えざるをえませんよね。ある意味では、生きているっていうこと自体が、生きていない状態から生きていない状態の「あいだ」です。もちろん、人間だけじゃなく、すべての生きものがその「あいだ」を生きているわけだけど、でも、それを生まれ前と死んだ後の間として「あいだ」を意識しているとなると、これはやはり、人間の特徴ということになるのかも。そもそも、「人間」という言葉自体が、人の「あいだ性」を示している、とよく言われますよね。
和辻哲郎は個人をまず最初に置く西洋個人主義に対して、人間は人と人との間があってこその人間だと考えた。人に限らず「もの」や「こと」などからなる、無数の関係性の網の目として人間を見る見方は古代から世界各地にあったんだと思います。そうすると、存在しているってこと自体が、ある意味「あいだ」である、という、さっきの話のようなことにもなる。
さて、お盆だということもあって、ぼくの兄が遺した文章を紹介させてもらいたいと思うんです。彼は建築家でして、実は今ぼくたちのいるこの建物(善了寺聞思堂)の設計をしたのも彼なんですね。自然建築といって徹底して自然素材を使う。伝統建築でよく使われた、木、藁、麻、葦、竹・・・。やがては全てが土に戻っていく、そういう建物を目指していました。そして彼が設計で注目していたのは、「あいだ性」なんですね。
都市、ランドスケープ、里山、そして建築について、いくつかの著作を遺しましたが、「あいだ」についての関心はとても強かった。例えば、家の内と外の「あいだ」としての縁側、窓、玄関、土間など。彼は「壁」というのも、単に外と内を隔てているんじゃなくて、外と内を繋具ものとして見ていた。家そのものが外との関係性の内にあるものなんじゃないか、そういうことを考えていた建築家なんです。
兄はまた長く成安造形大学という滋賀の大学で教えながら、近江学という地域研究にも熱心に取り組んでいたんですが、その彼が連載してきた『近江学』という雑誌に書いた最後の文章、言わば遺稿ですが、を読んでみたいと思います。これはお盆というものがなんだかわからない人のためにも、と思って用意してきた文章なんですよ。
古来より、集落を取り巻く山並みの向こうには先祖の霊が眠る他界が広がっていると考えられていた。お盆になると、祖霊がこの山を越えて村を訪れ、家族のもてなしを受けて再び山の向こうに還っていく。仰木では先祖の名前がはいったオショライさんと呼ばれる薄い板(経木)を仏壇に供えるが、昔はザシキの前の縁側にオショライさんを並べた盆棚を置いて先祖の霊の送り迎えをしたという。
縁側とは面白い場所だ。内と外を隔てるただの境ではない。ある想いが日常の生活圏からはみ出して、どこか遠い、見知らぬ世界に向かおうとする際の起点になっている。縁側があの世からの客を迎えたり送ったりするときの、家のターミナルポイントになっているのだ。
築山{ルビ:つきやま}とは、いわば身近な生活空間に創り出されたおしょらいさんのすむ山であり、他界の風景である。お月見もそうだが、昔の家にはこのように実に雄大なスケールの時空を超えた眼差しがあった。だが、どれも現代の住まいから失われてしまった視線だ。
里山は循環する魂のスミカ。家の中で、村の辻や道端の地蔵の前で、死者の魂と生きている者の魂が交感し合う終のスミカなのである
(大岩剛一「循環する魂のスミカ−仰木の里山から」『近江学』第11号、2019年1月10日発行、50頁〜51頁)
これは「循環する魂のスミカ」という文章の一部なんです。ここにはまず生者の世界と死者の世界、つまり他界との関係性が語られている。縁側って若者にわかるかな。あの縁側っていう空間、世界中にありそうでいて、実はなかなかないんですね。日本でも、今では滅多に見なくなった。内と外を繋いでいるっていうことが、縁側ほどわかりやすいものはないでしょう。
外から人が来て、中に誰がいようがいまいがそこに座っていたり、気づくとお茶が出てきたり、ベンチのようでもあり、一種のカフェみたいな領域でもあった。まあ、これは生きている人間同士をつなぐものですね。
それから兄が非常に注目していたのは、生き物たちです。庭っていうのは小さくても豊かな生態系で、そこには実にいろんな植物、虫たち、小動物たち、そして菌糸類から微生物までが暮らす場所だったわけで。「すむ」という言葉も「住」を使えば、人間が主人というような感じですけど、もう一つ、「棲む」がある。そうするともう少し生物界との繋がりが感じられる。兄はそれをよく言ってました。
この兄の文章の中に、先祖とか、祖霊とかが出てきますね。昔、鶴見俊輔さんが言っていたことを思い出します。柳田國男(1875~1962)が『先祖の話』の中で「先祖になる」ということを書いている、それがとても大事なんだ、と鶴見さんはよく言ってました。
柳田によれば、「ご先祖になる」ために人はよく生きようとしていたって言うんです。これはちょっと今では想像しにくい感覚ですよね。「人間があの世に入ってから後に、いかに長らえまた働くかということについて、かなり確実なる常識を養われていた」という柳田の文章があります。ここにも、よく生まれる前と死んだ後の「あいだ」としての人生という考え方が出ていますよね。
さて、この柳田の「先祖になる」という話を最近よく持ち出して刺激的な議論を展開する中島岳志さんです。どういうところで出てくるかというと、スペインのオルテガ・イ・ガセット(1883〜1955)やイギリスのG. K. チェスタトン(1874~1936)などのいう「死者の民主主義」についての話の中なんです。
どちらも保守主義と見なされた人たちですが、彼らは当時の民主主義の凋落について、今たまたま生きている人間たちだけで、なんでも多数決で決めたらいいんだという考え方こそが問題だと考えたわけです。その時々の生者の都合で憲法でも変えられちゃう。これが一番危険だと警鐘を鳴らしていたのがチェスタトンであり、オルテガだった。チェスタトンは死者たちにも投票権を、と唱えたほどです。彼らが危惧した通り、ナチス党は多数決で、“民主主義的に”政権についた。
そういう「死者の民主主義」という思想の流れがヨーロッパの中に本当はあった。そういうことをもう一回思い起こして再評価する必要があるんじゃないかっていうことを、中島さんは考えているわけですね。
死者にも投票をというと、馬鹿げていると思うかもしれないけど、実は、僕たちが生きているこの現実っていうのはみんな過去に生きていた人たちによって作られたものでできている。民主主義自体が今は亡き人々が遺した遺産ですよ。物だけじゃなく、制度も、言語も。その言語で考えるんだから、思想も。自分のものだと思っている心も実は過去の遺産です。伝統や文化の全体が死者たちの遺産です。こう考えると、生きている者だけしか視野に入れない自由とか民主主義って、一体なんだろう、ということになりますよね。
過去が、死者たちが見えないということは、未来が見えない、ということとも密接に関係していると思うんです。最近、16歳のグレタ・トゥーンベリの発言や行動が世界中で話題になっていますが、彼女が怒りと悲しみを込めて言っているのは、大人たちはまるで未来が存在しないかのように生きているじゃないか、ということ。
確かに死者たちを排除するやり方は、そのまま、まだこれから生きる人たちを排除することと表裏一体なのではないかと思うんです。グレタさんは言わば、これからの未来を生きる子供や若い人、さらにまだ生まれていない人たちを代弁しているんじゃないか。さっきの「死者に投票権を」に倣っていえば、未来の人々にも投票権をよこせ、ということになるでしょう。
さらに言えば、インドの物理学者で世界的な環境運動家であるヴァンダナ・シヴァが、伝統的な思想を基に創り出した「地球民主主義」、つまり、人間だけでなく、すべての生きものにも投票権を、という考え方にも繋がると思うんです・・・
大岩剛一先生のプロフィール
建築家(一級建築士)。成安造形大学造形学部教授。(有)ゆっくり堂役員。
東京生まれ。早稲田大学大学院修士課程修了。1977~99年まで東京で建築設計事務所を主宰、住宅・店舗を中心とする設計活動に従事。95年から環境NGO「マングローブ植林計画」のメンバーとしてエクアドル北西部沿岸地方、ベトナムでマングローブ保全のための研修・宿泊施設建設計画に携わる。
99年、環境文化NGO「ナマケモノ倶楽部」のメンバーとして、持続可能な社会に向けた住環境のあり方をテーマに活動する中でストローベイル・ハウスに出会う。2001年より「藁」と「スロー」をキーワードに、住の見直しと新しいライフスタイルの創造を視野に入れたスローデザイン研究会を主宰、「藁の家」の研究と普及に努めた。2019年4月永眠。
著書に『スローなカフェのつくりかた ~暮らしをかえる、世界がかわる~』 (共著、自然食通信社、2009)、『わらの家』(インデックス・コミュニケーションズ、2006)、『草のちから藁の家』(共著、INAX出版、2000)、『ロスト・シティ・Tokyo ~忘れられた風景からの都市論~』(清流出版、1995)、『大岩剛一とスローデザイン研究会の仕事』(スローデザイン研究会、2018)。