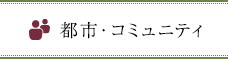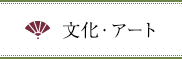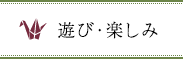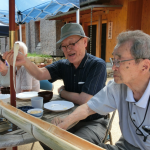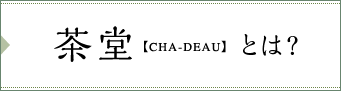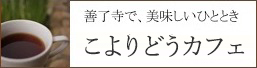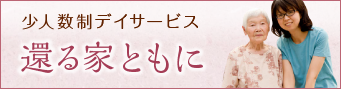- 人・暮らし
- 2016年12月31日
江戸時代の照明「行灯」の灯りから生まれた美意識とは
現代は、いつでもどこでも照明に明るく照らされて、町に暮らす人々にとっては、光がないという時間や場所がほとんどありません。利便性や治安のためには明るいほうがいいといわれていますが、江戸時代には、紙縒り(こより)に油を浸して火をつける「行灯」だけ、という生活が一般的でした。実際、江戸時代の人びとはどんな暮らしをしていたのでしょうか。
「闇」や「暗さ」から生まれた独自の江戸文化
江戸時代の人びとが使っていた「行灯」の光量は、豆電球ぐらいの明るさでした。現代人の感覚から言うと、その程度の明るさでは相当不便だったのではないかと思ってしまいますが、実は、明るくないからこそ「闇」や「暗さ」が注目され、独自な日本文化が生まれたのです。
「明かり」は孤独や幸せの象徴だった⁉
例えば、江戸時代の国学者・上田秋成の『雨月物語』では、闇と光の対比によって、人間のさまざまな感情を表しています。「菊花の約」という作品では、再会を約束した相手を待ち続ける青年の孤独を、「月が自分だけを照らしている」と感じ取るというくだりで、浮かび上がらせています。
また、「浅茅が宿」という作品では、長く留守にしていた夫が、家の中からの行灯をたよりに辿り着くと、戦で死んだはずの妻が出てくるという場面が描かれます。ここでは、暗闇の中での明かりが、暖かく懐かしいと同時に、刹那的で儚い「幸せ」の象徴であることが分かります。
このように、この時代の明るさと暗さのメリハリのある生活が、さまざまな解釈を生む日本文化の多様性を育んだといえるでしょう。
ろうそくの灯りで照らされた「吉原」は唯一無二のテーマパーク⁉
そうした文化の延長戦上に、江戸の有名な遊郭・吉原がありました。吉原では、ろうそくの灯りによって町や部屋を照らし、独特の幻想的な空間を作り上げていました。
大きなろうそくを夜どおしつけた幻想的な空間
例えば、吉原では、百目ろうそくという大きなろうそくを燭台に立てていました。当時、江戸の人びとには行灯の控えめな灯りや「夜は暗い」ことが当たり前だったので、ろうそくでも十分な明るさを演出することができたのです。しかも、夜どおしろうそくをつけていたのは吉原だけだったのだそう。来訪者たちは、吉原を世間より明るく、唯一無二のテーマパークだと感じていたのかもしれません。このようにして、闇があたりまえだったからこそ、光が魅力をもっていたんですね。
行灯で彩られた江戸の豊かな暮らし
吉原のように明るくなくても、庶民は、行灯の明かりで不便さを感じることなく暮らしていたようです。夜に食事をとるときでも、現代のように料理や酒をまわしてシェアするという習慣はなく、手元にあるお膳の中で事足りたので、困ることはありませんでした。また、裁縫も、糸さえ通せば、あとは手の感覚で十分にこなすことができました。
夜の暗さでも楽しめた書物や浮世絵
読書も、当時は、色の濃い墨で大きく書かれた文字の書物だったので、夜でも楽しめたといいます。カラーの挿絵や浮世絵に関しては、夜になって行灯の下で見ることを想定されていたのではないかと思われるような印刷(きら擦りなど)も。また、浮世絵の中には、月や行灯などわずかな明かりの下で逢瀬を愉しんでいる美女たちの姿を描いた、歌川国貞による「月の陰忍逢ふ夜」シリーズもあり、庶民たちが闇と光を楽しんで暮らしていたことがわかりますね。
江戸時代の美意識から現代社会を考えてみよう
このように、今からしてみたら不便に感じることも、江戸時代の価値観では、不便とも貧しいとも危ないとも感じていませんでした。現状を当然なものと考えて「便利」なだけを追い求めるのではなく、かつてのような美意識や価値を感じることができれば、ずっと少ないエネルギーで、安心かつ安全な社会で暮らすことができるのではないでしょうか。
参考:
- 『未来のための江戸学』(田中優子著、小学館101新書)